私の気に入った鍔の部屋 その2
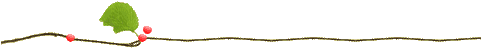

|
「 蜃気楼の図 」 鍔 銘 太龍斎 光良(花押) | ||
|
|||

|
「 蜃気楼の図 」 鍔 裏面 (Tsuba) | ||
|
|||
 |
「 節分の豆撒きの図 」 鉄地 鍔 (刀装具) | ||
 |
|||
 |
|||
| 「節分」 特に立春の前日の称。この日、鰯(いわし)の頭を 柊(ひいらぎ)の小枝に刺して戸口にさし、 炒り豆をまいて悪疫退散、招福の行事を行う風習がある。 冬から春への境として物忌みに籠ったのが本来の行事。 銘 在川斎真 製 ? 鉄地に、金銀胴、四分一、赤銅の象嵌 片櫃 小振りなため脇差に使用。(縦68mm横幅62mm) |
|||
 |
「節分の豆撒きの図」 四分一地 縁頭(刀装具) | ||
 |
|||
 |
|||
悪鬼・疫癘(えきれい)を追い払う行事。 平安時代、宮中において大晦日(おおみそか)に盛大に行われ、 その後、諸国の社寺でも行われるようになった。 古く中国に始まり、日本へは文武天皇の頃に伝わったという。 節分に除災招福のため豆を撒(ま)く行事は、追儺の変形したもの。鬼やらい。 ( 頭 ) マスを持ち、力強く 豆を 蒔かんとする人物 ( 縁の差し表 ) 逃げる鬼、( 裏 ) 御簾に 投げた豆(金点象嵌) 四分一磨き地 縁( 縦38mm 横幅19mm 高さ9mm+ 左手 )、頭( 縦34mm横幅15mm ) |
|||

|
「貝尽くし」 鉄地刀装具 | ||
|
トップページへ/戻る/次の鍔へ
 | ご意見/お問い合わせはこちらまで |
@nifty ID:UHI02711





