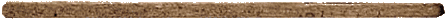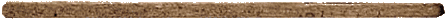私の気に入った鍔の部屋 ( 刀 KATANA 2 )
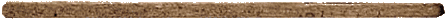
 |
「 助宗 」 一尺六寸七分(50.6㎝)
南妙法蓮華経 草の倶利伽羅 (彫) 脇差 |
|


刀身 白鞘
|
[刀身] 一尺六寸七分 (50.6㎝) 、反り1.2cm、目釘穴 2個、脇差
南妙法蓮華経. 草の倶利伽羅 彫、 特別貴重刀剣
銘 「 助宗 」
鎬造り、脇差
僅かに刷り上げ お題目は、持ち主の死生観を表し、
仏の加護を、求めたもの。
戦国時代。駿河の国、現在の静岡県島田市。
|
|
 |
「 翁助宗作 」 一尺三寸一分
菖蒲造り 脇差
|
|


刀身 白鞘
|
[刀身] 一尺三寸一分 0厘、反り三分0厘、目釘穴 壱個、脇差
銘 「 翁助宗作 」
助宗、菖蒲造り ( 梵字 剣、細い棒樋 )
太刀銘に切る、特異な形、代を譲った隠居後の作か
身幅広く ずっしりと重い脇差。
持ち主は、どのような拵えで、腰に差した傾奇者か、想像が尽きない。
駿河の国、現在の静岡県島田市、藤枝市。
|
|
 |
「 嶋田住清兵衛義助 永禄二年二月日 」 (21.6cm)
おそらく造 短刀
|
|


刀身 白鞘
|
[刀身] 21.6cm、反り0.0cm、目釘穴 2個、おそらく造 短刀
銘 「 嶋田住清兵衛義助 永禄二年二月日 」
おそらく造 短刀
銘が長銘であることから注文打ちであることが判る、
清兵衛義助は二人いるが、古い時代の清兵衛義助です。
この義助は、甲州に赴いても、駐鎚している。
参考までに 武田晴信が、剃髪して入道となり、
信玄になった年が、永禄二年。
翌、三年(1560年)桶狭間の戦いで、今川義元が尾張の織田信長に敗死。
武田信玄の右手(馬手)差しの 助宗の おそらく造は、よく知られている。
助宗の おそらく造は 五振り確認されていると聞く。
他に廣次などの同時期の相州鍛冶に おそらく造があり、
その時代、一時期流行る。
江戸期の百科事典の発行まで、おそらく造りの作刀は、間が空く
戦国時代。駿河の国、現在の静岡県島田市。
|
|
近隣の博物館
藤枝市郷土博物館
佐野美術館 ・ 島田市博物館
[ 義助 ] 刀匠島田顕彰碑 石碑のみ
中里の庄 ・和(なごみ)藤枝市の山間の隠れ家
アフリカでボランティア、さやかさんのブログ
Hi ! TAKARA and EIGO
Let's practice together.
トップページへ/戻る/刀-3/ 鍔のページへ